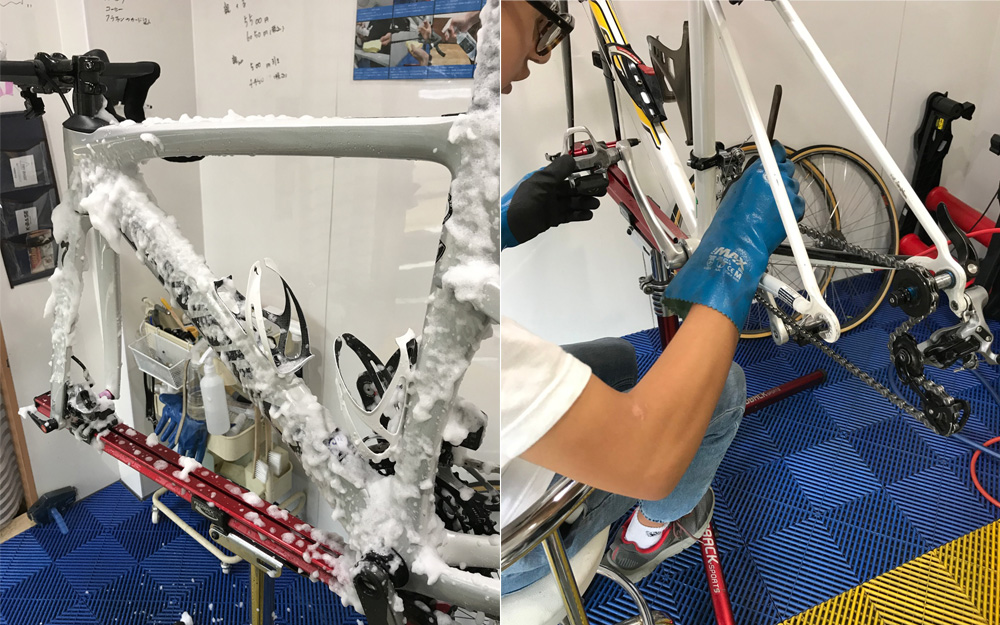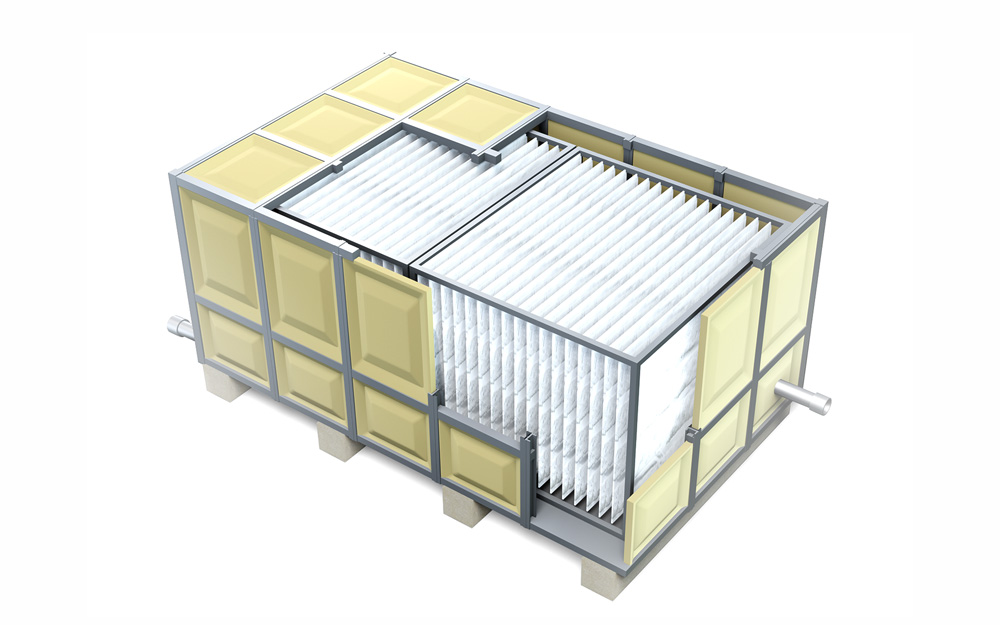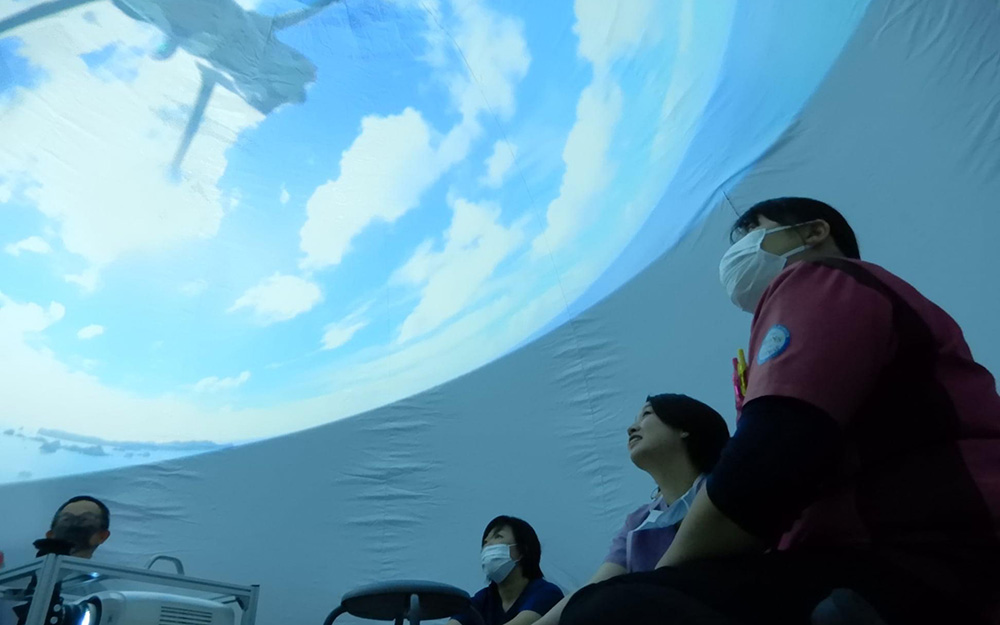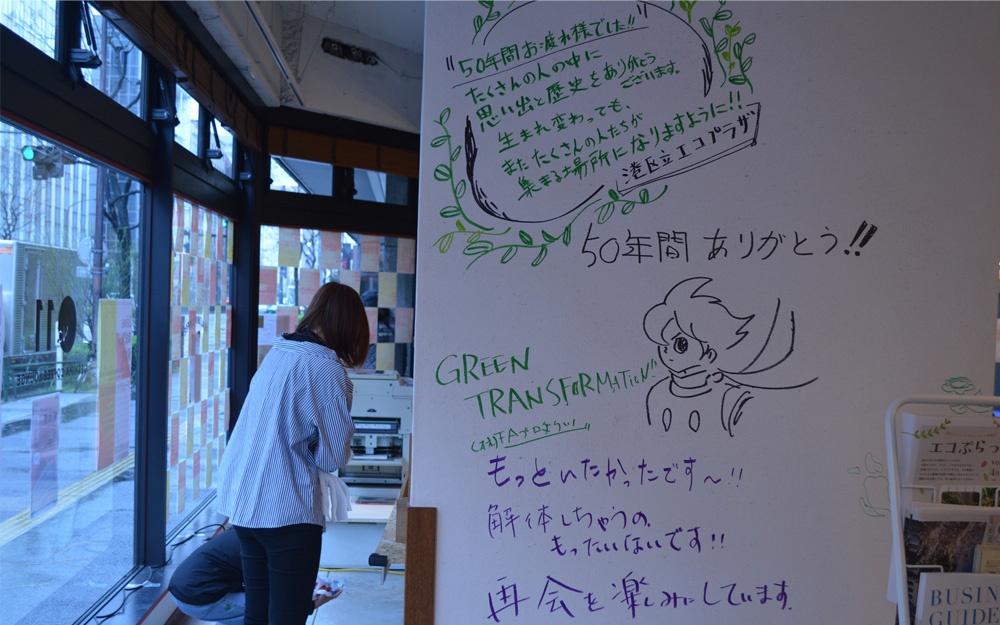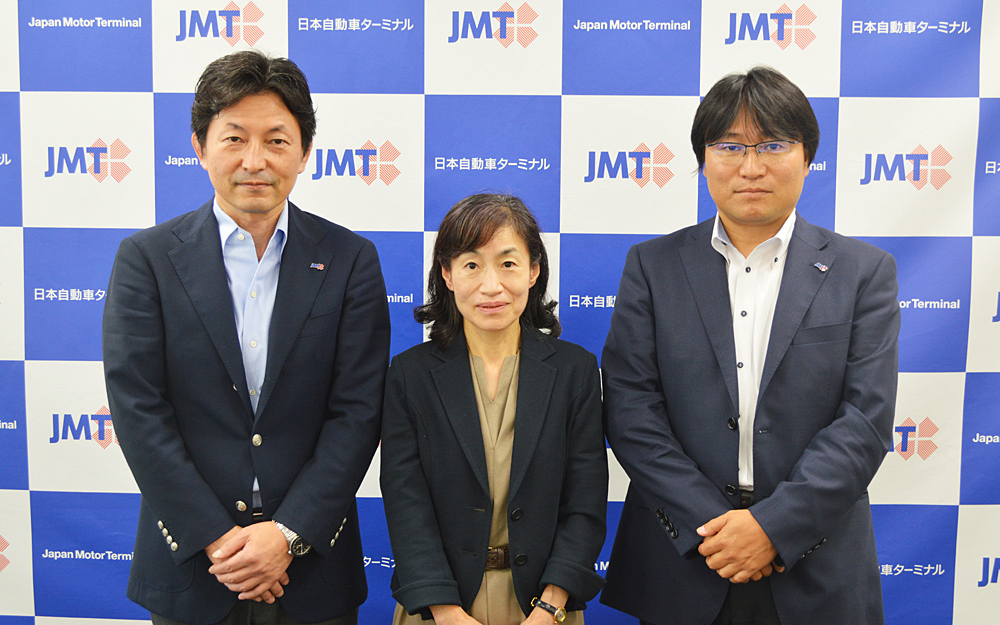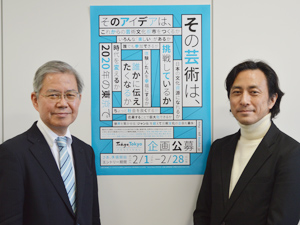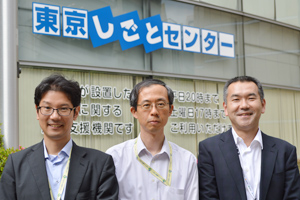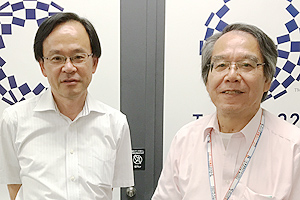最新号のご紹介2025年8月20日号
-
 トップインタビュー Vol.212日本財団職員 東京2025デフリンピック応援アンバサダー 川俣 郁美さん
トップインタビュー Vol.212日本財団職員 東京2025デフリンピック応援アンバサダー 川俣 郁美さん -
 局長に聞く197水道局長 山口 真氏
局長に聞く197水道局長 山口 真氏 -

・各会派が知事に面会 都政の前進に意欲
・Town Topics<23区26市5町8村>
・ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢
・仕事に命を賭けて Vol.205 航空自衛隊第4航空団第11飛行隊
・社会に貢献するために 第65回 株式会社アクト