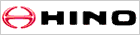好きだからこそ続けられる。
舞台美術家
朝倉 摂さん
画家として数々の受賞に輝き活躍する一方、1948年、「パーティー」(ジェーン・バロウ演出)を第1作に舞台美術の世界へ。以来、現在にいたるまで革新的な演劇とかかわり続け、日本の戦後現代演劇を代表する舞台美術家として活動している。表現するということ、自由ということ、現代の日本の演劇シーンについて、舞台美術家の朝倉摂さんにお話をうかがった。
(インタビュー/津久井美智江)
アートに垣根はない
好きだと思う気持ちあればこそ

「暗くなるまで」写真撮影/樋口茂子
――お父様が彫刻家で、芸術に囲まれてお育ちになりました。絵画の道に進み、さらに舞台美術の世界に入られたのは、やはり家庭環境の影響が大きかったのでしょうか。
朝倉 環境はあまり関係ないのではないでしょうか。
私はもともと芝居が好きで、若いときから本当によく観ていました。ですから、芝居にかかわる仕事は、いつかはやりたいとは思っていました。
――映画のお仕事もなさっていますが、それぞれ異なる点はございますか?
朝倉 絵にしても舞台にしても映画にしても、ものをつくる、表現するという点で、私にとってはみんな同じです。外国ではずいぶん絵描きさんが舞台装置を手がけているんですよ。ピカソもやりましたしね。アートに関しては、垣根はないんじゃないでしょうか。
まあ、日本の場合は、何かというと決め付けたがりますがね。この人は絵描きだ、この人は彫刻家だとか。そのほうが楽ですからね。
しいて言えば、絵は一人で描けますが、芝居や映画は一人ではできないことでしょうか。いずれにしても、どれも好きだからやっていますし、続けてこられたと思います。
――本当にたくさんの作品を手がけていらっしゃいますが、作品を選ぶ基準というのはあるのでしょうか。
朝倉 先方からお申し出があるわけで、私のほうから出かけていって「やらせてください」ということはありません。われわれの仕事は、日本でいうところの裏方。要するに本(戯曲)の持っている意味を、一つの空間の中にビジュアルとして構築するためにある。あまりでしゃばってやるものではないと思っています。
――多くの人たちと一緒に一つの作品をつくっていくうえで大事なことは?
朝倉 結局はプロデューサーでしょうね。今の日本には、プロデューサーなるものが、そうはいない。
中根公夫さんというプロデューサーがいらして、蜷川幸雄さんの若い頃の作品を何本かご一緒しましたが、芝居に対する情熱がぜんぜん違います。『ハムレット』の最後の稽古のときのことですが、衣装が重いので少し軽くしたいと。その意見には私も賛成でしたが、30人からの役者が出ている芝居ですから、直すのは大変なんですよ。でも、自らそれをやる。もちろんデザイナーも含め、スタッフ総出で手伝いましたが、明け方までかかってもやる。決して労を厭わないんですね。それが本当のプロデューサーだと思います。
やはり芝居が好きなんです。好きでなきゃできないです、あんなこと。今のプロデューサーはそんな馬鹿なことやらないでしょう。やはり馬鹿なことをやるのは大変なことだと思いますね。
自分とは、自由とは……
一人の人間として考えることが大事

「動物園物語」写真撮影/樋口茂子
――1970年にロックフェラー財団の招きでニューヨークに渡られました。
朝倉 私たちのころは、ロックフェラー財団の偉い人が一人日本に来て、個人的にピックアップしていました。レポートとかも何もなし。武満徹さん、横尾忠則さん、池田満寿夫さんといった方々と一緒に私も選ばれて、何のことやらさっぱり分からないまま、とにかく行ってみたらいいんじゃないかと思って。ほんとに何も考えずに行った次第です。
今も日本をはじめアジア各国の若い人たちをたくさん招いていますよ。
――あちらでは、どんなことを学ばれたのですか?
朝倉 丁寧に芝居を観たり、関係する人たちに会って話をしたり……。日本人のようにここから先が勉強とか、ここから先が遊びだとは考えない。まず生きていることが素晴らしいと。刺激的で、面白かったですね。
日本に戻ってからも、また遊びに行った際に「この芝居を見たい」と言えば切符を取ってくれますし、人も紹介してもらえます。
本当のお金持ちは、考え方が違うんでしょうね。それに税法も違う。たとえば、美術館などに絵を寄付しても、寄付したことに対して一切税金はかからない。だから、いいものがどんどん集まるんです。
――実際、ニューヨークの「メトロポリタン美術館」は、いろんな方の寄付によっている部分が大きいですよね。
朝倉 そうですね。寄付された作品には、寄付した方の名前が全部書いてありますし、「ロバート・レイマン・コレクション」という、個人の名前が冠された展示スペースもあるほどです。
ハーレムの北のハドソン川沿いに、メトロポリタン美術館の分館としてロックフェラーがつくった「クロイスターズ」というミュージアムがあるんです。中世ヨーロッパのいくつかの修道院を移築した建物で、すごくきれいなところ。そこには近代的な建物が一切ないの。どうしてなのかとロックフェラーの方に聞きましたら、視界に入るところに汚いものを建てたくないと。全部自分の土地なんですよ(笑)。
――日本のお金持ちとは桁が違いますね。ニューヨークに比べて東京、ひいては日本の演劇シーンはいかがですか?
朝倉 観る側もつくる側も、レベルの低さは歴然としてありますね。だいたい商業演劇なんて言葉、外国にはないですから。あるとしてもブロードウェイ、オフ・ブロードウェイ、オフオフ・ブロードウェイという区別であって、オフやオフオフ・ブロードウェイのほうがより純粋なものをやっているという程度の違いです。
それから、アメリカは全部の大学に劇場がある。以前、セントルイスで仕事をしたのですが、そこの大学にもオペラハウスがありまして、とても素敵だなと感じたのは、切符切る人も何をやる人も全部ボランティアということ。日本だと、そんなことしても何の得にもならないと、すぐに損得で考えますでしょう。
――確かにアメリカではボランティアが日常生活の中に溶け込んでいます。自分が貢献できることに対して、労力を惜しみません。
朝倉 自由や権利を主張するけれど、義務もきちんと果たすという意識が高いのだと思います。つまり、自分とはいったい何なのか、自由とはどういうことかということをちゃんと考えている。結局はその人自身の資質によるのでしょうけれど、考えることはとても大事だと思います。
ピカソの有名な言葉があります。自由とは何かと問われて、「自由とは鳥かごの中に魚が泳ぎ、金魚鉢の中に鳥が羽ばたく。それが自由だ」と。哲学的な言葉で分かりにくいかもしれませんが、そういうことなのかもしれません。
ですからニューヨークに行くと本当に自由だなと感じますね、街を歩いていても、人と話をしていても。
ふだんの暮らしの中に
もっとアートを取り入れてほしい
――今はどんなお芝居を手がけてらっしゃるのですか?
朝倉 『ヤマトタケル』。市川猿之助さんがずいぶん前にやったものを、今回は若い人たちのバージョンで。その後に『四人姉妹』という芝居があります。
――やはり再演になると舞台美術なども変えるのですか?
朝倉 舞台装置はあまり変わりませんが、役者が違いますから、細かいことはいろいろ変えます。
それから、劇場が変わる場合はすべて変わりますね。たとえば下北沢の本多劇場でやるのと池袋のサンシャイン劇場でやるのとでは、大きさが倍以上違いますから、そのように変えないと。
パルコ劇場もそうですが、本多劇場ができたときは本当に新鮮でした。紀伊國屋ホールとか、あのくらいの劇場はやりやすいですね。
――大きさもあるでしょうが、どこが違うのですか?
朝倉 客席に勾配があるんですよ。日本の劇場は、歌舞伎座にしても新橋演舞場にしても平べったい。おそらく絵巻物を見る感覚なんでしょうね。
――なるほど。確かにヨーロッパの劇場はアリーナになっています。ところで、舞台美術を考えるときに、どうやってインスピレーションを得るのでしょう。
朝倉 そりゃあ、あなた、しゃべれないわよ(笑)。舞台を観ていただくよりほかないんじゃない?
――はい、ちゃんと劇場に足を運びます(笑)。それにしても映画館で映画を見る、劇場で芝居を見るということが、今の日本では特別なことになってしまっていますね。
朝倉 ちょっと前までは農村歌舞伎なども残っていて、芝居というものが身近にありました。普通の人の普通の暮らしの中にごく自然にあったはずなのに、いまや文化財や遺跡のようになってしまった。
四国の金比羅座など昔の歌舞伎舞台が復活していますが、技術や技法は伝承しなければなくなってしまいます。文化はちゃんと伝えていかなければならないと思いますね。
![[プロフィール参照]](img/nt200803_02001_04.jpg)
撮影/赤羽真也
<プロフィール>
あさくら せつ
1922年、彫刻家、朝倉文夫の長女として台東区下谷に生まれる。41年、第4回新文展に初入選。人物群像を発表するが、のち抽象的作風に転じる。48年より舞台美術の仕事を始め、以後、前衛劇からオペラまで幅広く活躍。55年「近松心中物語」「盟三五大切」などでテアトロ演劇賞、61年「にごり江」で芸術賞を受賞。82年「日本映画アカデミー賞」優秀美術賞(篠田正浩監督、映画『悪霊島』の美術)など数々の賞を受賞。著書に「朝倉摂舞台空間のすべて」「朝倉摂のステージワーク1991―2002」などがある。イラストレーター、装丁家としても活躍。