環境配慮から太陽光発電事業を開始
ドローンを活用したメンテナンス事業も
株式会社シービーエス
首都圏を中心に、全国および海外のビルや商業施設、ホテル、官公庁などのメンテナンス(清掃・設備業務)、工事、設計、プロパティ&ファシリティマネジメント、業務支援など多岐にわたる業務を行う株式会社シービーエス(以下、CBS)。ここ数年は「環境」をキーワードとした新規事業にも積極的だが、今号では太陽光発電事業に注目。10年以上を経た現在の同事業の実情とともに、同社だからこそ可能になる新しい事業展開や社会貢献の取組にも迫った。
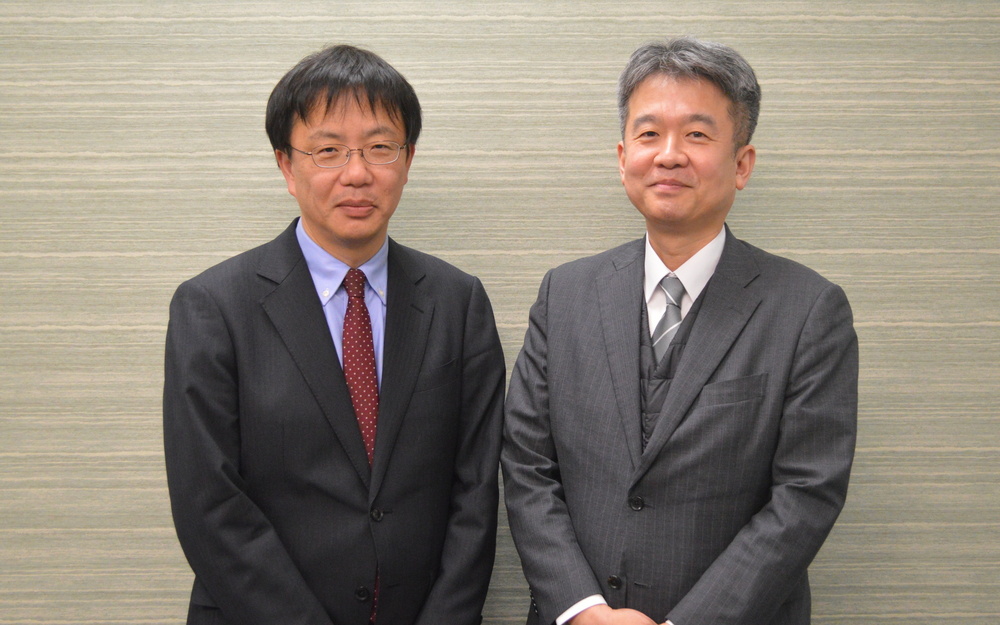
株式会社シービーエス執行役員であり巡回・再生エネルギー環境事業部の冨沢浩部長(右)と同事業部再生エネルギー環境事業課兼巡回事業課の向武志課長
東日本大震災がきっかけ 広島、栃木、茨城で運用
2013年、CBSはメガソーラー(=1メガワット以上の大規模太陽光発電)事業に着手した。事業参入の背景には、2011年に起こった東日本大震災があると、同社執行役員巡回・再生エネルギー環境事業部の冨沢浩部長は語る。
「弊社はビルをはじめとする様々な建物や施設のメンテナンスを行ってきましたが、そのなかに原子力発電所の管理も含まれていました。それまで日本の電力の主軸を担っていた原子力発電システムが、東日本大震災によりストップし、電力不足に陥りましたが、我々が管理するビルや施設への影響も大きく、新しい電力の必要性を痛感しました。そこで、原子力に代わり、次世代の環境にも配慮した電力として、太陽光発電に着目し、事業化に着手しました」
震災翌年の2012年、国も太陽光発電の推進を打ち出し、買取制度がスタート。その翌年から同社もメガソーラー発電所の設置が可能な土地取得に動き出した。結果、広島県東広島市、栃木県壬生町、茨城県阿見町に土地を確保し、現在も発電とともに電力の供給を行っている。土地取得から現在に至るまで本事業に関わっている、再生エルギー環境事業課および巡回事業課の向(むかい)武志課長は、当時を振り返る。
「メガソーラー発電所の設置には、発電機器が設置できる土壌の状況、安定した日照立地など様々な条件が挙げられますが、特に弊社としてこだわったのは、森林伐採をしないことです。あくまでも環境に配慮した事業を推進することが重要で、契約した3箇所はどこも伐採せずに設置することができました」

「阿見太陽光発電所」(茨城県阿見町)(提供:CBS)
地域ごとに異なる設置技術と管理が必要 10年以上培った経験を元に新規事業に
3箇所はそれぞれの立地により異なる特徴があり、その地域に適した発電機器の設置と周辺への対応が求められると、向課長は言う。
「たとえば、東広島は住宅公社の一部スペースを取得しました。そのため、日当たりもよく、森林伐採の必要がありませんでしたが、当然ながら住宅が近く、住民への理解が求められました。一方、栃木は採石場跡地で、周辺住民などへの対応の心配はありませんでしたが、採石場という特性上、特殊な設置技術が必要でした。その点、茨城は飛行場跡地だったため、機器設置も比較的容易でした」
また、設置後のメンテナンスも土地ごとに対応が異なるが、それぞれのノウハウを生かし、2022年からは他のメガソーラー発電所の維持管理事業も新規事業として開始したという。
「メガソーラーのメンテナンスで重要なのは、こまめな清掃による発電効率の向上と、広大な敷地の除草、故障機器の発見・修理です。特に故障機器の発見は、長方形などの探しやすい形状の土地の場合はいいのですが、東広島のように複雑で見通しが悪い立地だと時間がかかり、見落としがちです。そこで、弊社はグループ会社の秋山写真工房の知見を生かし、ドローンによる赤外線カメラを用いた検査システムを開発し、新規事業としてサービスを開始しました。温度のムラから異常の違いも区分けできる高精度の検査が、発電を止めずに、短時間に広範囲で可能になります。メンテナンスに特化した事業者は少ないので、今後問い合わせが増えていくことを期待しています」(向課長)

「壬生町太陽光発電所」(栃木県壬生町)(提供:CBS)
周辺住民のための出張授業が地域の環境教育推進にも
ただ、近年は新たな課題も発生していると、冨沢部長は言う。
「メガソーラー発電機器の配線の盗難が増加し、そのセキュリティコストが大きな課題になっています。また、弊社が事業を開始した当初よりも、国の売電価格の買取額が半分以下にまで下落しています。ですが、太陽光発電の拡大は日本の環境問題に大きく貢献すると確信しています。地道な改善を重ね、安全性や収益性を両立できる形を目指していきたいと思います」
実はこの発電事業の延長線上で、新たな地域貢献の形が生まれつつあると、向課長は言う。
「先にも触れましたが、東広島の発電所は住宅が近く、住民の皆様への理解を促すために、近隣の小学校への出張授業を年1回行ってきました。また、地域イベントでも太陽光発電のPRブースを出してきました。
出張授業は、当初は弊社が子どもたちに太陽光発電の仕組みを伝えるものでしたが、子どもたちの学習能力と意欲が想像以上に高く、自ら熱心に研究し、逆に私が教えられることもあります(苦笑)。学校ではそれを良い環境教育の機会と捉えてくださり、感謝のコメントを集めたパネルを作ってもらったりもしました」
メガソーラー発電所をきっかけに、地域の環境教育が進展し、事業者と地域の信頼関係も深まり、さらに環境に配慮した電力が広がる。こうした好循環を生み出すことも、これからの太陽光発電事業では重要になるのかもしれない。

「グリューネン入野第1・第2太陽光発電所」では、近隣小学校で出張授業を行っている(広島県東広島市)(提供:CBS)



