能楽も茶道も終わりのない孤独な道を、
一生かけて歩んでゆく。

能楽シテ方宝生流 職分 茶道裏千家 正教授 関 直美さん
茶家に生まれ、家業を継ぐものと思っていた。ところが、深く考えもせずに口にした「ビジネスウーマンになりたい」という一言からお茶の世界を飛び出して、東京、そしてニューヨークへ。そこで日本文化の奥深さを認識した。帰国後は茶家を継ぐも、友人の誘いで初めて観た『関寺小町』に衝撃を受け、能楽師になることを決意。昨年、重要無形文化財保持者(総合認定)に認定された能楽シテ方宝生流職分であり茶道裏千家正教授の関直美さんにお話をうかがった。
初めて観た秘曲中の秘曲『関寺小町』が人生を変えた。
—お能とは無縁の茶道の家に生まれたそうですね。なぜ能楽の道に進まれたのですか。
関 33歳になる年に、あるお能の舞台に出会ったんです。それが、金春流七十九世宗家金春信高先生が喜寿のお祝いとして演じられた『関寺小町(せきでらこまち)』で、私の人生を変えることになりました。
数ある能の演目の中でも、老女を描いた曲は最奥の秘曲として大切に扱われていて、三老女と呼ばれる『檜垣(ひがき)』『姨捨(おばすて)』『関寺小町』は特別な曲なのですが、その中でも最高位の曲とされるのが『関寺小町』です。
初めて見たお能で、軽い気分転換のつもりで拝見したんです。
ところが、その舞台の後半、小野小町を演じていたシテの信高先生が倒れられた。あまりにもゆっくり倒れられたので、初めは舞の一部かと思ったのです。が、3度目に倒れられた時、とうとう後見の方が舞台の前方に進み出て、信高先生を奥の後見の座の位置まで抱きかかえていかれ、長袴姿で続きを舞われた。それはそれは衝撃的でした。
—後見は舞台の後ろに座っていて、時々シテのそばに行って装束の乱れを直したり、小道具を片付けたりするだけで、一見何もしていないように見えます。
関 何事もないから何もしないだけであって、ひとたび何事か起これば、後見が出てきて対処するんですよ。お能の舞台は、一度始まったら最後までやめることができません。後見は舞台で行われるすべてのことに責任を持ち、無事に終わらせる責任を持っているんですね。
『関寺小町』は、100歳になった小野小町の物語です。若い時には歌の名人といわれ、その美しさで名を馳せ、宮中の男性から言い寄られと、華やかな世界を生きた女性です。でも、100歳になった彼女は歌もうまく詠めず、舞を舞うこともできない、物乞いに成り果ててしまっている。
後で知ったことですが、信高先生は、『関寺小町』を舞うために、約2年間、家元としてどうしても出演しなければならない舞台以外はほとんどお断りになり、弟子の稽古もすべて休まれて、稽古に集中されたそうです。
それほどの想いをもって臨まれた舞台なのに、途中で倒れてしまい、断念せざるを得なかった。先生の無念さはいかばかりだったでしょうか。
私はその舞台の直前に母を亡くし、次いで父も亡くしていましたので、生老病死にとても敏感になっていたんですね。『関寺小町』の舞台に出会って、生きること、老いる哀しみ、病気となる苦しみ、そして死について考えずにはいられませんでした。人間の一生は、砂上の楼閣のようなものなのかと、心に響きました。
—信高先生はご無事だったのですか。
関 後に信高先生のご子息の安明先生がおっしゃるには、面の紐を強く締めすぎたのではないか、舞台上では汗もかくので面がキリキリしまり、呼吸が苦しくなったのではないかとのことでした。

昨年の自主公演では大曲『井筒(いづつ)』に挑んだ
先生方の大きな懐の中で勉強できる 年に一度の自主公演は大事な経験。
—それにしても30歳を過ぎてからの入門はあまりにも遅く、あまりにも無謀では?
関 それは同じ伝統文化である茶道の家で育った私が一番よく知っています。でも、一度火がついた心をどうしても抑えることができなかった。いろいろ調べてみると、東京藝術大学(藝大)の音楽部邦楽科能楽専攻に入れば、能楽の家の生まれでなくても能楽師になる道が開かれていることがわかったんです。周りの反対を押し切り、自分の心のままにお能の世界に飛び込んだのですが、お茶の家に生まれながらも外の世界に憧れ、与えられた環境を飛び出してニューヨークに行ったことが大きかったと思います。
私、あんまり深く物事を考えない質なんですよ。とりあえずやってみよう、だめだったらまたやり直せばいいと思ってニューヨークに行ったのですが、そこで自分のアイデンティティとかオリジナリティを持つことの大切さを思い知らされました。よく外から見ると、日本のことがよく見えてくると言いますが、私もニューヨークで暮らす中で、日本という国が唯一無二の国であり、日本人は類まれな民族だということを理解するようになったのです。
そして、どれだけユニークか、個性があるか、人と違うか。人と違うということは、人と比べても意味がないということ。だから自分は自分なのだという精神を20代に植え付けられましたので、世襲の家の生まれの方が王道を行く能楽の世界にあって、女性であるとか、遅く始めたとか、そういうことを考えることなくやってこられた。だからこそ今ここにいることができるのだと思います。
—藝大では博士課程を修了されています。そこまで極めるのは大変だったのでは?
関 正直、私は修士課程までと思っていたんです。あと1年でようやく終わると思っていた時に、教授から博士課程はどうですかとすすめていただき、あと3年、私44歳になっちゃうと思ったのですが、お声をかけていただけるということはありがたいことですし、舞台は経験を積んでなんぼです。
藝大は人間国宝であったり、各流儀の宗家の方がご指導に来られているので、そういう方々にお相手をしていただける。そして1年に1回は舞台に立てる。それはすごく魅力でした。それで博士課程を受験することを決意しました。
—どんなに勉強したり、稽古したりするよりも1回の舞台のほうが大事なのですね。
関 具体的に何ということではないのですが、舞台に立って気づくことはすごく多いと思います。やはり稽古では装束をつけるということはありませんし、面も、普段は自分が持っている稽古面をかけて稽古をしますから、本番の装束、面、お客様がいらっしゃるという環境、それからお囃子方や地謡の先生とは1回お申し合わせをいたしますが、やはり本番になると全然変わります。
私は年に1回自主公演を開催しているのですが、家元にお許しをいただければ曲も自分で決められますし、ワキ方や囃子方、地謡を謡ってくださる先生も自分で決めることができます。先生方の大きな懐の中で勉強させていただける。本当にありがたいことで、私が自主公演を続けているのはそれが理由です。

裏千家の正教授として茶道の普及にも尽力
演者は稽古どおりに動くだけ、お能は観る側の想像力に任されている。
—舞台でやってみたい、あるいはお好きな曲は?
関 最初の自主公演の時にも舞わせていただいたのですが、綺麗な曲というより『鉄輪(かなわ)』のような普通の人間の情感が溢れ出るような曲が好きです。
—情感溢れるといっても、面をつけて表情をなくし、動きも限られています。どうやって情感を表現するのでしょうか。
関 よく聞かれるのですが、私が恨みに思ったり、悲しく感じたりするわけではなくて、お客さまが感じることなんですね。ですから日々お稽古をして、本番は稽古どおりに動くだけ。そこに私の感情というものは多分含まれていないです。
—つまり、お能は観る側の想像力に任されていると。
関 ご存知の通りお能は舞台に何も置いてありません。最初にワキ方が出てきて、自分は何々で、ここはどこどこという場所ですと言ったら、お客様は、この人はどういう人で、場所はこんなところなのかなと想像する。だから、お客様が500人いれば500通りのお能があるのだと思います。
—「伝統の橋がかり」という団体を立ち上げ、伝統文化を普及、継承する活動にも力を入れていらっしゃいますね。
関 日本には能楽をはじめ、茶道、華道、書道、武道などたくさんの伝統文化があります。そんな日本の伝統文化を伝えていくために、様々な分野で活躍されている先生方をつなぐ架け橋になれればと思い、2014年に設立しました。
最初に取り組んだのは「夏休み伝統文化親子教室」です。次代を担う子供たちのために、普段接する機会の少ない能楽と茶道の体験教室を企画しました。
伝統文化は敷居が高いと思われていますが、子供には敷居自体がありません。袴をつけてあげただけで感激しますし、「舞って楽しい!」と言ってくれます。お茶も、そんなに難しいことはしなくても、おいしいお菓子とお抹茶をいただくだけでいいのです。
子供だからどうでもいいのではなく、子供だからこそちゃんとしたものを観せて、味わわせて、伝統文化はこんなにいいものなんだと教えることが大事なのだと思います。だから、子供の教室は手を抜くことができませんし、とても疲れます(笑)。
—昨年、重要無形文化財の総合認定を受けられましたね。
関 本当に感慨深いです。でも、ようやくスタート地点に立ったところ、まだまだこれからという感じです。 この世界に入って25年くらい経ちますが、今、能楽師として活動させていただけていることが奇跡で、感謝しかないといつも思っています。
—最後にお能の一番の魅力とは?
関 ゴールがないことではないでしょうか。同じことを繰り返し繰り返しやって、少しは上手くなったかなと思っても、録画などで見返すと、まだこんなに下手だったのかと思う。ゴールが見えず、この道はどこまで続くんだろうと思いながら、やり続けるしかない。完全を目指すのかもしれませんが、完全ではない道をずっと歩き続ける。そのプロセスが、「道」というものなのなのかもしれませんね。
私は、実は飽きっぽいんですよ。小さい頃にピアノやバレエ、書道などいろいろ習い事をやりましたが、続きませんでした。でも、お能には飽きたことがない。何でも真剣にやろうと思えば、自己と対峙することになります。能楽も茶道も、終わりのない孤独な道を、多分一生かけて歩んでゆくのだと思います。

小学生から70代まで多くの人に能を教えている
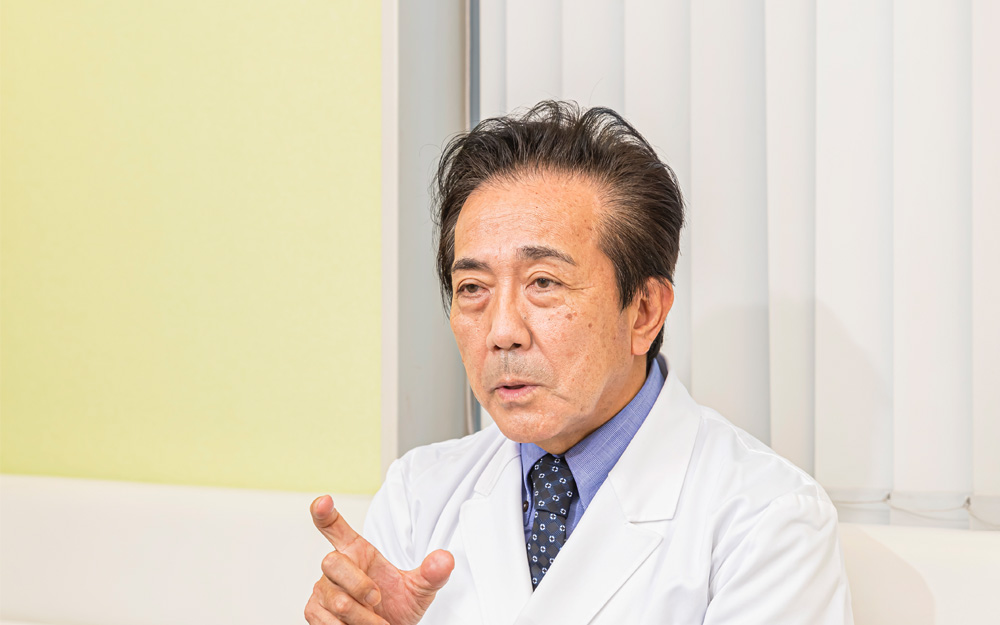
情報をお寄せください
NEWS TOKYOでは、あなたの街のイベントや情報を募集しております。お気軽に編集部宛リリースをお送りください。皆様からの情報をお待ちしております。



