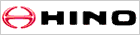東京都には、標高2000mを越す雲取山から亜熱帯性気候を持つ小笠原諸島まで、実に変化に富んだ森が分布している。森林面積は都全体の3分の1強を占める。東京の水や緑の鍵をにぎるともいえる林業。残念なことに衰退の一途を辿っているが、経済重視から持続可能な社会へと人々の関心が移りつつある昨今、林業を見直すいい時期なのかもしれない。
(取材/中本敦子)
東京の林業の変遷

整備された人口林には陽も差す
縄文時代、多摩地域では、実のなる木を植えて、ドングリやクリの実などを主食にしていたといわれている。
江戸時代に大火があり、その復興材として、はげ山になるほど沢山の木が多摩の森から伐り出された。その結果、多摩川の水害をもたらし、流域の村や集落は度重なる災害にみまわれる事態となった。
そこではじめて江戸幕府は山林の重要性に気付き、「木を植え育てて利用する」という育成林業の考え方を導入した。その後、森林は復元。土地の劣化はくい止められ、流域での農業は安定し、生態系も保全された。
このように日本は、昔からその土地にあった方法で森林を活かし、かかわりを持ちながら暮らしてきた。 江戸の都が大人口を擁し、その後の大都市東京の成長を支えてきたのは、森が生み出す木材や林産物という自然の恵みを大切に育み、生活のさまざまな局面で上手に利用してきたからなのだ。
しかし、戦後の復興で再び多摩の林は大量に伐採された。昭和30〜40年代に再び植林したものの、その後日本の林業の低迷で、林業をやめる人も多く、山林の整備が進まないのが実状だ。さらにシカの増加により、食害を受け、かつてのようなはげ山現象が広がりつつある。林業の荒廃、山林の衰退は、深刻な問題となっている。
低迷からの脱出に向け
都の森林面積は、平成19年4月現在、約7万9000haで、総面積の3分の1強を占める。うち、約6割がスギやヒノキの人工林で、全国(46%)に比べて、高い人口林率となっている。

グラフからもわかるように、そのほとんどが戦後の復興時期に植えられたものだ。すでに木材として使える樹齢となっているのに、伐採されずに残っている木も多い。30年以上たったスギは、花粉の量が増え、花粉症の原因ともなっている。
木材価格のグラフを見ると、右肩下がりで推移しているのがわかる。山元立木価格というのは森林所有者に入る金額であるが、平成9年までは1万円を超えていたが、16年では2000円に落ち込んでいる。1haの木を切って、その後整林すると180万円くらいかかるが、2000円という金額では60万円くらいにしかならず、売れば売るほど赤字になる。

多摩産材人称マーク
林業従事者だけではこの状況を変えることは不可能だ。都では林業が産業として回っていくように、政策を進めている。まずは、コスト削減できるように基盤整備を進めること。そして、東京の木材の需要が増えるように推進していくこと。都の公共施設で多摩産材を利用したり、多摩産材人称マークを支援するなどしている。

多摩産材を使ったベンチ
実際に産業として回るようになるには、時間がかかるだろう。都民としては山林の大切さを理解し、林業を応援する気持ちを持ち続けていきたい。