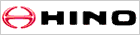酒の味もビールの味も、ぐっと引き立つ。
写真提供:東京カットグラス工業協同組合
ガラスの表面に繊細な模様がきらめく切子。カットグラスとも呼ばれ、麻の葉、矢来(やらい)、格子、魚子(ななこ)といった模様を、回転する砥石車でガラスの表面に彫りつけていく。線が縦、横、斜めに交差する菊籠目(きくかごめ)など複雑で高い技術を要するものも多く、いずれも江戸時代から受け継がれてきた手技である。
日本に現存する最古のカットグラスは、正倉院に所蔵されている白瑠璃碗(はくるりわん)で、ペルシア(イラン)で作られ、日本へ運ばれた。同時に古代ガラスの製法も日本へもたらされたが、材料が入手困難だったため、10世紀頃には日本から姿を消してしまったという。
再びガラス製造が日本に登場するのは、天文18(1549)年、フランシスコ・ザビエルが宣教師として来日したときである。ポルトガル語のvidroから、ガラスはビードロと呼ばれるようになった。
江戸切子が初めて作られたのは大伝馬町でビードロ屋を営んでいた加賀屋九兵衛であったといわれる。天保5(1834)年、九兵衛はガラスの表面を紙やすりに使われる砂(こんごうしゃ)で削ることに成功した。その技術はかなり高度なもので、嘉永6(1853)年、ペリーが浦賀に来航した際に加賀屋の切子細工が献上されたという記録が残っている。当時、江戸切子は高級品で、諸大名をはじめとする裕福な人々の間で贈答品として珍重された。加賀屋の引札(ひきふだ=カタログ)には皿、蓋物、鉢などの食器のほか、さまざまな切子細工の製品が描かれている。
ちなみに薩摩切子は、江戸末期に28代薩摩藩主島津斉彬が、城内で色ガラスの製法を研究させ、青、紫、黄など各色のガラスで器物をつくり好評を博した。しかし、斉彬の急死と薩英戦争による工場焼失で、薩摩切子はわずか数十年で姿を消し、幻の存在となってしまった。
ふだんは缶ビールをそのまま口に運んでしまいがちだが、今宵は江戸切子に冷酒を注ぎ、江戸期から続くガラスの美しい模様が織りなすきらめきを肴に、キュッと一杯やるのもいい。